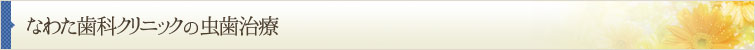

初期段階では自覚症状が殆どないため、気付いた時には奥深くまで進行していることが多く、早期発見・早期治療が要となってくる病気です。
昔に比べて虫歯の数は減りましたが、現在でも抜歯した人の30%以上が虫歯が原因で歯を失っています。(8020推進財団・全国抜歯原因調査 / 2005)
当院では、ただ虫歯を治療するだけでなく、再発防止・予防のために虫歯のしくみや予防法などをしっかりと患者さまにご説明しています。
また、患者さまにお口の状況を理解していただいた上で、よく話し合って治療計画を立て、できるだけ削らない・痛みの少ない治療を心がけています。
生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中には、虫歯の原因となる細菌は存在しません。しかし、ほとんどの方が成長していく過程で虫歯の原因菌に感染してしまいます。
虫歯の原因菌がお口の中にいる人の中でも、特に虫歯になりやすい人・なりにくい人がいます。
いったい何が違うのでしょうか?
虫歯の原因菌は、お口の中の食ベかすを元に酸を作り出します。その結果、お口の中が酸性に変化し、歯が溶ける「脱灰」と呼ばれる現象が起こります。虫歯の原因菌は、私たちの食後にもっとも活動が活発になるのです。
しかし、食後しばらくすると唾液が持つ「緩衝作用」によってお口の中は酸性から中性に戻り、今度は歯を修復する「再石灰化」が起こります。
私達のお口の中では、この「脱灰」と「再石灰化」が毎日食事のたびに繰り返しおこなわれています。
もし食後の「脱灰」で歯が溶けてしまっても、歯を修復する「再石灰化」が追い付いていれば、一方的に歯が溶け続けることはありません。
虫歯になりにくい人は、「再石灰化と脱灰のバランスが十分にとれている」と言えるでしょう。
逆に、虫歯になりやすい人は「脱灰と比べて再石灰化が少ない」ということになります。
では、なぜ脱灰と再石灰化のバランスが崩れるのでしょうか?
実は、再石灰化をおこなうには、脱灰以上に時間がかかるのです。そのため、間食が多いと再石灰化の修復が起こる前にふたたび脱灰がはじまり、結果としてお口の中は「いつも歯が溶けている」状態になってしまいます。
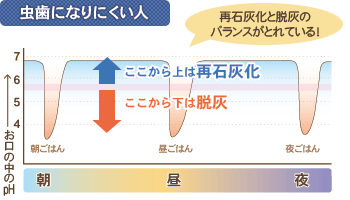

虫歯になりやすい方の傾向として、以下が挙げられます。
このいずれかに当てはまる方は、歯みがきといったホームケアはもちろんのこと、生活を改善し歯科医院でプロによる歯のクリーニングなどをおこないましょう。
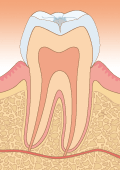 【CO】
【CO】
表面が溶けて白く濁り、歯が透明感を失った状態です。痛みはありません。
歯科医院では、ブラッシング指導とともに、再石灰化を促して自然治癒を目指します。この段階では歯は削らず、歯を強くするフッ素を塗付し強い歯質を作ります。
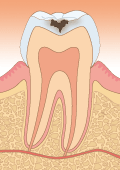 【C1】
【C1】
虫歯が進み、歯の表面の白いエナメル質が溶けはじめた状態です。
COと同様、ブラッシング指導で再石灰化を促進し自然治癒を目指します。
エナメル質には神経がないため、この段階でもまだ痛みはありません。
正しいホームケアを行い、虫歯の進行を抑えられれば削らずに済みます。
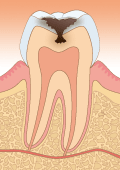 【C2】
【C2】
エナメル質のさらに内側の象牙質にまで虫歯が進行した状態です。
象牙質はエナメル質より柔らかいため、一度虫歯が到達すると進行は早く、徐々に痛みや冷たい物がしみるなどの自覚症状が出てきます。
この段階では、虫歯に侵された象牙質を除去して詰め物をします。
 【C3】
【C3】
虫歯がさらに進行し、大きな穴が開いて歯髄(いわゆる『歯の神経』『歯の根っこ』)にまで到達した状態です。炎症を起こしズキズキと激しい痛みがあります。この段階では、虫歯に侵された歯髄と象牙質を除去し、歯髄のあった根管を除菌・清掃(根管治療)します。
ここで根管をきちんと除菌し、新たに菌が入らないように密封することで、歯を残せる可能性があります。
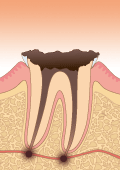 【C4】
【C4】
歯冠部(歯の頭の部分)が溶けてしまい、歯根だけが残った状態です。
すでに歯髄は死んでしまっているため痛みは感じません。
虫歯が深く進行している場合、歯根の先に袋状に膿がたまり、歯を残すことも困難になります。
歯を残せる場合には根管治療を行い、被せ物で修復しますが、残せない場合には、ブリッジや入れ歯、インプラントによる治療を行います。
虫歯がC3、C4の段階になると、細菌に感染した歯髄を除去する根管治療が必要になります。
これがいわゆる「歯の根っこの治療」です。
時間がかかることもある治療ですが、感染した組織をきれいに取り除かない限り、何度でも虫歯が再発する可能性があるため、歯を残すために欠かせない大切な治療です。
 【SREP 1】
【SREP 1】
C3の状態。虫歯が歯髄まで進行しています。
一度細菌に感染した歯髄を治すことは困難で、放置すると根尖病巣などのさらなる悪化を招きます。
そのため、感染歯髄を全て取り除く(神経をとる)治療をおこないます。
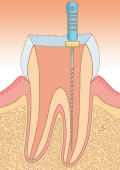 【STEP 2】
【STEP 2】
リーマーやファイルと呼ばれる細長い器具で、細菌感染してしまった歯髄や根管の壁などを取り除きます。
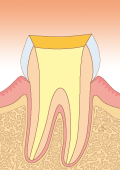 【STEP 3】
【STEP 3】
細菌感染してしまった組織を取り除いたら、中に薬を入れて消毒します。(完全に消毒できるまで、何度もこれを繰り返します)
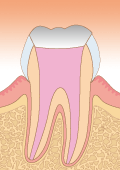 【STEP 4】
【STEP 4】
根管の消毒が完全に終わったら、根の先を充填剤で封鎖し、薬を入れて密封します。虫歯の大きさや噛み合わせに応じて、詰めものや被せ物をします。
歯医者と言えば、「痛そう」「怖そう」……そんなイメージの方も多いのではないでしょうか。
虫歯の進行を止めるためには、どうしても虫歯になった部分や、感染してしまった歯髄を除去しなければなりません。そのためには麻酔が必要ですが、この麻酔注射の痛みが苦手という方もいらっしゃるかと思います。
当院では、歯科治療における患者さまの負担を少しでも軽減するために、さまざまな工夫をおこなっています。
 針による注入ではなく、歯肉に直接塗布することで効果を発揮する麻酔です。歯科治療において、唯一避けられない痛みが麻酔注射の針を刺す時だと言えるでしょう。
針による注入ではなく、歯肉に直接塗布することで効果を発揮する麻酔です。歯科治療において、唯一避けられない痛みが麻酔注射の針を刺す時だと言えるでしょう。
当院では麻酔注射の前に、注射針を刺す場所へキシロカインを塗布する予備麻酔をおこないます。
 当院では、体温と同等に温めた麻酔液を使用しています。
当院では、体温と同等に温めた麻酔液を使用しています。
麻酔注射の痛みは、体温と麻酔液の温度との差とも関係しています。温めた麻酔液を使用することで、より注射時の痛みを緩和させることができます。
 麻酔注射の痛みは、溶液を注入するスピードや圧力に大きく左右されるといわれています。当院では、コンピューター制御により痛みの少ない理想的なスピードで麻酔液を注入してくれる電動麻酔注射器を導入しています。
麻酔注射の痛みは、溶液を注入するスピードや圧力に大きく左右されるといわれています。当院では、コンピューター制御により痛みの少ない理想的なスピードで麻酔液を注入してくれる電動麻酔注射器を導入しています。
表面麻酔と併用することで、麻酔注射時の痛みを大幅に軽減してくれます。
大人も子どもも関係なく、「歯医者さんが苦手」という方はいるものです。
精神的な苦痛は肉体的なものへとつながりやすく、治療の痛み・不安が原因で歯医者さんへ足が遠のき、歯を失ってしまうという方もいるようです。
当院では、丁寧な説明と丁寧な治療はもちろんのこと、そういった患者さまにも安心して治療が受けていただけるように、患者さまとよく話し合った上で治療計画や治療方法を決定しています。
少しでも不安を取り除き、患者さまにリラックスして治療を受けていただけるように心がけています。
虫歯のなりやすさ(カリエスリスク)には、さまざまな要因が関係しています。
治療の後、また新しく虫歯が出来るかどうかは、その人の食生活、歯質、口腔内の虫歯の原因菌の数などが関わってきます。ご自分のカリエスリスクを知り、どのような歯みがき方法、食生活をすれば虫歯を防げるのかを知ることが大切です。
当院では、歯みがき指導の他、
自覚症状のほとんどない虫歯を早期に発見し予防するために
患者さまに定期検診をおすすめしています。
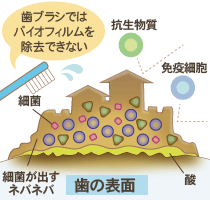
虫歯の原因菌にとってお口の中は理想的な環境です。食べかすを放置していると、虫歯の原因菌たちは有機汚染物質などで出来たネバネバの中に入り込んで増殖し、バイオフィルムを作り出します。
細菌たちの要塞とも言えるバイオフィルムに守られながら、細菌はどんどん増殖して酸を放出し、虫歯を悪化させていきます。
バイオフィルムは細菌を外部から守るバリアを兼ねているため、歯みがきや抗生物質でも完全に除去することは困難です。
きれいに除去するためには、歯医者さんで歯のクリーニング、つまりプロフェッショナルケアをおこなうことが必要です。