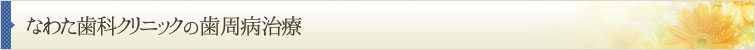
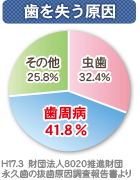
虫歯は菌の酸で歯が溶けていきますが、歯周病は歯と歯肉の間に細菌が入り込むことによって周囲に炎症を起こし、最終的には歯肉の奥にある顎の骨が溶けていく病気です。
顎の骨が溶けはじめると、歯は支えを失って次第に抜け落ちてしまいます。
歯を失った原因のうち、その40%が歯周病によるものだという統計が出ています。(8020推進財団・全国抜歯原因調査 / 2005)
歯周病は、初期段階での自覚症状がほとんどないために、海外ではサイレントディシーズ(静かなる病気)と呼ばれています。ギネスブックには「人類史上最も感染者の多い感染症」として歯周病が掲載されており、日本では35歳~44歳の人の80%が歯周病にかかっていると言われています。
さらに、歯周病は進行すると顎の骨と歯を失うだけでなく、お口を通じて原因菌が体内に侵入することで、全身に影響を及ぼすことが分かってきました。
歯周病を治療することでお口の健康を保つだけでなく、さまざまな全身疾患を防ぎ、改善することに繋がるのです。
| 【歯周病が影響する可能性のある病気・トラブル】 | |
|---|---|
| 糖尿病 | 糖尿病になると抵抗力が落ち、歯周病の悪化を招きます。さらに、歯周病になると血糖値が上昇し、糖尿病のコントロールを困難にします。 歯周病と糖尿病は、互いに症状をより悪化させる関係にあります。 |
| 誤嚥性肺炎 | お口の中の細菌が肺に入って引き起こされる肺炎を誤嚥性肺炎と言います。歯周病であったり、口腔ケアが不十分だと起こりやすくなります。抵抗力の落ちた高齢者に多い病気です。 |
| 細菌性心内膜炎 (感染性心内膜炎) |
歯周病の歯肉を通じて血液中に紛れ込んだ細菌や細菌の作り出した有害物質が、心臓の弁膜付近に菌が増殖する原因となり、感染性心内膜炎を引き起こすと言われています。 |
| 虚血性心疾患 (心筋梗塞・狭心症) |
血液中の細菌が血管で炎症を起こすことにより、動脈硬化の原因となる可能性があります。動脈硬化は心筋梗塞や狭心症を引き起こします。 |
| 内臓疾患 | 血液を経由した細菌によって内蔵で炎症が起こり、腎臓病や肝臓病などの原因になると言われています。糖尿病との合併症が懸念されます。 |
| 早産や低体重児出産 | 歯周病になると、原因菌に対する免疫反応の中で陣痛を起こす物質を発しやすくなるため、歯周病が早産や低体重児出産の危険性を高めることがわかっています。 |
歯周病は自覚症状に乏しい病気ですが、本人が実感できる症状として以下のようなものが挙げられます。
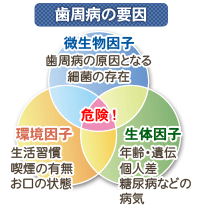 歯周病はお口の中にいる原因菌だけでなく、お口のケア、食生活、ストレスなど、さまざまな要因に左右される「生活習慣病」です。
歯周病はお口の中にいる原因菌だけでなく、お口のケア、食生活、ストレスなど、さまざまな要因に左右される「生活習慣病」です。
普段はそうでもないのに、仕事が忙しい時、体調の悪い時だけ歯肉が腫れるということはありませんか?私たちは日頃、目に見えない細菌から免疫力によって自分の体を守っています。体調が良い時、ストレスのない時は免疫機能が十分に働いているために気にすることはありませんが、日常生活の乱れ、ストレスの増大などをきっかけに自律神経のバランスが崩れ始めると、免疫力が弱まり歯周病の症状が強く現れはじめます。
歯周病を防ぐには、お口のケア以外にも食生活や睡眠など日常生活の見直し、禁煙、ストレスの改善など、日頃から免疫力を高める生活をすることが必要です。
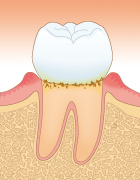
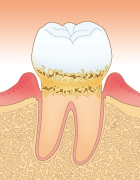
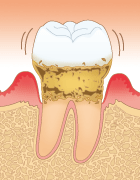
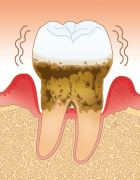
歯周病は、症状の程度に応じて歯肉炎と歯周炎の2つに分類されます。
歯肉炎が進行すると歯周病となり、歯周病は歯槽膿漏とも呼ばれます。
| 歯肉炎 | バイオフィルム(細菌・歯垢・歯石)が歯と歯肉の間に入り込み、周囲に炎症を起こしている状態です。 歯と歯肉の間の溝は深くなり、歯周ポケットが形成されています。歯肉がうっすらと赤く腫れ、出血することもあります。この段階では自覚症状は殆どありません。 定期的な歯科医院でのPMTC(歯のクリーニング)と正しい歯みがきで改善できます。 |
|---|---|
| 歯周炎 (歯槽膿漏) |
歯肉炎が進行したことにより、歯肉だけでなく歯を支えている歯根膜や歯槽骨が破壊され始めた状態です。歯肉は腫れ、出血しやすくなり、口臭を伴うことがあります。放置すると、歯がグラグラと揺れ始め、最終的に抜け落ちてしまいます。 改善には歯科医院での本格的な治療が必要です。 |
歯周病には自覚症状が少ないため、早期発見には定期検査が必要です。
歯肉の腫れや出血、歯のぐらつきがなくても、歯科医院で定期的に歯周病検査を受けるようにしましょう。
当院では、初診時と定期検診の際に歯周病検査をおこなっています。
●問診
ご家庭での生活習慣、お口のセルフケアについてお聞きします。
歯周病は生活習慣病ですので、喫煙・飲酒の有無、食生活、仕事によるストレスなどに関してもお聞きしています。

プローブという器具を用いて、歯周ポケットの深さを検査します。
健康な歯肉 : 深さが~2mm以下
初期 : 深さが3mm~5mm
中期 : 深さが5mm~7mm
重度 : 深さが7mm以上
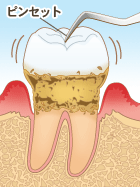
ピンセット等を用いて、歯の動揺度(ぐらつき具合)を調べます。
0度 : 正常。歯の仕組みとしての動きのみでほとんど動かない。
1度 : 初期歯周病の状態。わずかに動く程度。
2度 : 中等度歯周病の状態。前後・左右に動揺がみられる。
3度 : 重度歯周病の状態。前後・左右と上下にも動く。
この場合、抜歯の可能性が高い。

レントゲン撮影では、歯槽骨の状態や歯周組織の炎症状態を知ることができます。進行した歯周病は複数の歯に渡って炎症が起こるため、パノラマレントゲンを用います。
●口腔内プラーク検査
プラークを赤く染める歯垢染色剤を歯面に塗布し、プラークの付着状況をチェックします。
これにより、日頃の歯みがきがどの程度出来ているか、お口の中のどの部分の歯みがきが苦手なのかを知ることができます。
●位相差顕微鏡
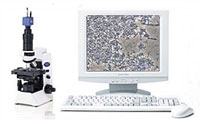 当院には位相差顕微鏡もございます。
当院には位相差顕微鏡もございます。
位相差顕微鏡は、患者さまから採取したプラークを用いてお口の細菌を実際に観察することが出来る特殊な顕微鏡です。
これにより、患者さまの持っている歯周病の原因菌、カビの種類を知ることができます。
さらに、細菌の種類や菌の多さから、歯周病になりやすいかどうかや、お口の中の歯周病の進行度程度を知ることができるため、治療計画を立てる際に役立つ設備です。
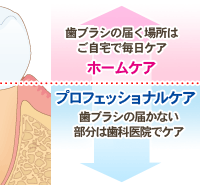
歯周病の症状は、お口の中を清潔に保つことで改善されます。そのため、歯周病の治療はなによりも「お口の中の掃除」が大切です。
歯の歯肉より上の部分はご自宅での歯みがき(ホームケア)でもきれいにすることができますが、歯周ポケットの中、つまり歯肉に隠された部分は、歯科医院での治療(プロフェッショナルケア)でしかきれいにすることができません。
歯周病の改善においては、患者さまと歯科医院が協力し、ホームケアとプロフェッショナルケア両方を充実させることが必要になります。
●PMTC
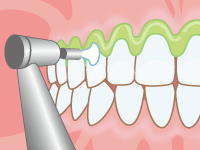 歯科医院の専門家による歯のクリーニングでは、日頃の歯みがきでは落とせないバイオフィルムや歯石を落とすことができます。PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)は歯科医師や歯科衛生士が専用器具を用いておこなう、専門的な歯や歯の周囲(歯周組織)のクリーニングです。歯周ポケットを清潔に保つことで、歯周病を予防できる上、口臭や歯の着色(黄ばみ)を改善する効果もあります。
歯科医院の専門家による歯のクリーニングでは、日頃の歯みがきでは落とせないバイオフィルムや歯石を落とすことができます。PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)は歯科医師や歯科衛生士が専用器具を用いておこなう、専門的な歯や歯の周囲(歯周組織)のクリーニングです。歯周ポケットを清潔に保つことで、歯周病を予防できる上、口臭や歯の着色(黄ばみ)を改善する効果もあります。
●スケーリング(歯周組織のクリーニング)
歯の表面に付着しているバイオフィルムをスケーラーという器具できれいに除去します。バイオフィルムは自宅の歯みがきだけで完全に除去することはできません。また、一度除去してもしばらくすると再付着します。定期的に歯科医院で除去してもらいましょう。
●ルートプレーニング(歯根面のクリーニング)
スケーリングの後、細菌汚染されたセメント質や象牙質を取り除くのがルートプレーニングです。歯石やバイオフィルムの再付着を防ぐため、仕上げとしてざらざらになった歯根面を滑らかにします。
●ブラッシング指導(歯みがきの説明と練習)
 ご自宅でのホームケアが不十分な場合、歯科医院でどんなにきれいに清掃してもお口の中はすぐに不衛生になってしまいます。歯周病の改善においては、毎日のご自宅での歯みがきが歯科医院のプロフェッショナルケアと同じくらい大切です。当院では患者さまが日頃されている歯みがき方法の改善点を一緒に見つけ出し、患者さまそれぞれのお口に合った効果的な歯みがき方法を指導しています。
ご自宅でのホームケアが不十分な場合、歯科医院でどんなにきれいに清掃してもお口の中はすぐに不衛生になってしまいます。歯周病の改善においては、毎日のご自宅での歯みがきが歯科医院のプロフェッショナルケアと同じくらい大切です。当院では患者さまが日頃されている歯みがき方法の改善点を一緒に見つけ出し、患者さまそれぞれのお口に合った効果的な歯みがき方法を指導しています。
歯科医院の指導によるご自宅でのケア、歯科医院でのスケーリング・ルートプレーニング、定期健診などでも歯周組織に回復が見られない場合、外科的な手術で対応します。
●歯周ポケット掻爬術
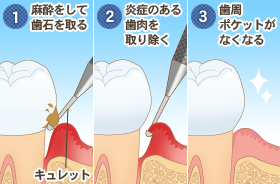 軽い歯周病に対しておこなう治療です。麻酔を使用して歯石を取った後、スケーリング・ルートプレーニングと同じキュレットという器具を用いて歯周ポケット内の炎症している歯肉の表面を取り除きます。メスは使用せず、歯肉は切開しません。
軽い歯周病に対しておこなう治療です。麻酔を使用して歯石を取った後、スケーリング・ルートプレーニングと同じキュレットという器具を用いて歯周ポケット内の炎症している歯肉の表面を取り除きます。メスは使用せず、歯肉は切開しません。
●フラップ手術
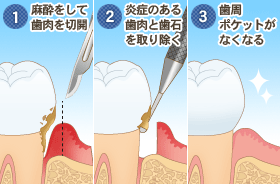 重度の歯周病に対しておこなう治療です。歯周ポケットが深すぎて歯石を完全に除去することができない場合に、歯肉を切開して直接目で確認しながら、奥深くの歯根のプラークや炎症している歯肉を取り除きます。歯槽骨の汚れや歯肉の感染部位をきれいに取り除くことで、歯周組織の回復を促します。
重度の歯周病に対しておこなう治療です。歯周ポケットが深すぎて歯石を完全に除去することができない場合に、歯肉を切開して直接目で確認しながら、奥深くの歯根のプラークや炎症している歯肉を取り除きます。歯槽骨の汚れや歯肉の感染部位をきれいに取り除くことで、歯周組織の回復を促します。
この他、重度の歯周病で歯のぐらつきが酷い場合には、そのまま歯が抜け落ちてしまうことを防ぐために応急処置として隣接する歯同士を固定する「暫間固定」という処置をおこないます。
また、周囲の歯への影響を考慮した上でより多くの歯を残すために、場合によっては数本を抜歯することもあります。