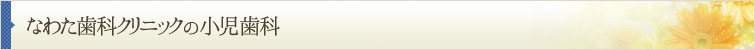

日々成長する子どもたちのお口の中は毎日絶えず変化しています。
大人の歯への生え変わりを筆頭に、歯並びや顎の骨の大きさも年を経るごとに変化し、その子の状況や環境に応じて虫歯になりやすい場所も変わってきます。子どもの歯は大人の歯と違って柔らかく、虫歯になると進行も早いため、気が付いたら大きな虫歯になっていた、ということもあります。
当院の小児歯科では、虫歯予防はもちろんのこと、「すべての乳歯が抜けてから永久歯に生え変わるまで」をしっかりと管理することを重視しています。歯の生え変わりの時期に永久歯を正しい位置に生やすことでかみ合わせを整えて、子どもたちが大人になってからも身体やお口が健康で過ごせることが私たちの目標です。
いつか抜け落ちる乳歯だからといって虫歯を放置すると、正しく噛めないことによる咀嚼不足から顎の発達が遅れ、後に永久歯がきれいに生えてくることができません。顎の発達が遅れることは、歯並びの悪化から骨格にまで影響を及ぼすのです。さらに、乳歯の虫歯が進行して永久歯のもとになる歯胚(しはい)を傷つけると、永久歯の形成不全や変色を招きます。
永久歯が生えてから虫歯に気をつければいい、というのは大きな間違いなのです。
当院の小児歯科は、子どもたちと信頼関係を築くことからスタートします。
ほとんどのお子さまにとって、歯科医院は『痛くて怖いところ』でしょう。歯科医院に来ただけで怖くて泣いてしまう、逃げたくて暴れてしまうお子さまを、無理矢理ユニットに座らせたり、押さえつけて治療をおこなうようなことをすれば、お子さまにとって歯科医院は絶対に行きたくない場所になってしまうかもしれません。
お子さまの将来のためにも、小児歯科でお口の健康を守っていくのは大切なことです。治療を進めていくためには、お子さまの歯科医院に対する不安と恐怖を取り除いていくことが何よりも必要なのです。
当院では、初診では本格的な治療はせずに応急処置のみをおこない、ユニットに座ってお話をしたり、診療室の雰囲気や機器に馴染んでもらうことで、まず歯科医院に対する不安を少しずつ取り除いていきます。最初のうちは、歯科医院は怖いところではなく、安心できる場所だという認識を持ってもらうことに重点を置いて接していきます。
お子さまが診療室に十分に慣れてきたところで、治療に入ります。最初のうちは隣に保護者の方が付き添っていただくことも可能ですし、練習しながら治療をおこなっていきます。
このように段階的に進めていくことで、ほとんどのお子さまが最終的には一人で治療をおこなえるようになります。
その他、絵本やおもちゃを用意するなど、お子さまができるだけリラックスした状態で治療に入れるよう環境を整えております。
【1】できるだけ早く歯科医院で診てもらう。
ベストなのは、虫歯ができる前に歯科医院へ連れて来ていただくことです。
フッ素塗布や健診をおこなうだけであれば、歯科医院は怖い場所というイメージを抱かなくなり、いざ治療になった場合にも、歯科医院と信頼関係を築いた上でスムーズな治療がおこなえます。
【2】歯科医院に対する怖い先入観を与えない。
子どもというのは素直なもので、歯科医院への先入観が来院・治療のしやすさを左右することがあります。保護者の方は、「悪い子は歯医者に連れてくよ」「ちゃんと歯みがきしないと歯を削られちゃうよ」など、お子さまを怖がらせるような表現は避けてください。歯科医院は怖いところだというイメージが一度刷り込まれてしまうと、なかなか払拭することが難しくなります。
また、日頃そのようなことを言っていると、いざ虫歯になり治療することになった際、「歯医者さんは怖くないよ」と言ってもお子様は不信感を抱きます。
【3】お子さまと治療内容の約束をしない。
お子さまを連れて歯科医院へ来院する際に、お子さまに「今日はみるだけだよ」「歯は削らないよ」などとごまかして連れてくるのはやめましょう。実際に歯科医院で治療が必要になった時、お子さまは「みるだけだって言ったのに!」と不信感を抱くことに繋がります。
また、別の場所へ行こうと言ってお子さまを歯科医院に連れてきても、心の準備ができない分お子さまを余計に怖がらせ、傷つけてしまうことになりかねません。
前もって保護者の方が「虫歯菌退治してもらおうね」「歯をきれいにしてもらおうね」など、分りやすい言葉でお子さまに伝えることが大切です。
【4】頑張ったことを褒めてあげる。
歯科医院での治療が終わったら、お子さまを必ず褒めてあげてください。たとえ泣いてしまったり、暴れたとしても「よくがんばったね!」「一人でできてすごい!」などと褒めてあげることで、お子さまに自信がつき、次回のスムーズな治療へとつながります。この際、来院時に付き添った保護者の方(仮にお母さま)だけではなく、父親また祖父母への電話報告など、家族皆で褒めてあげるのが効果的です。
がんばった後に褒めてあげることで、次もがんばるという意欲に繋がり、お子さまの精神的な成長を促します。

当院では、虫歯予防の第一歩として保護者の方向けに「仕上げみがき指導」もおこなっています。
歯みがきは、虫歯を予防する上でもっとも効果的で大切な予防方法です。お子さまに合った歯みがき方法を覚えて、しっかり磨いてあげましょう。
お母さまをはじめとした周囲の保護者が、お子さまの歯の健康をきちんと管理してあげることがとても大切です。
当院では、痛くない仕上げみがきの方法を、仕上げ専用歯ブラシを使ってわかりやすくご説明します。お子さまに合った歯ブラシを使用することも大切ですから、ご希望の方には最適な歯ブラシもお選びしています。
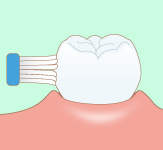
子どもの乳歯は小さめの歯ブラシを歯に平行にして当て、小さな力で小刻みに動かして磨く横みがきが基本になります。力を入れすぎたり、大きく歯ブラシを動かすと、歯肉を傷つける恐れがありますので、ご注意ください。歯と歯の隙間や、歯と歯肉の境目、奥歯などは特に丁寧に磨いてあげてください。歯みがきが嫌いにならないように、話しかけながらやさしく磨いてあげましょう。
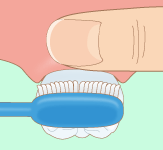
子どものお口の中はデリケートなので、「しっかり磨かないと!」と思って力を込めると、痛がったり歯肉を傷つけてしまうことにつながります。お子さまが仕上げみがきを嫌いにならないように、できるだけ優しく、歯肉に歯ブラシが当たらないようにみがきましょう。
コツとしては、歯肉に指をあて、それに沿って磨いてあげると、歯ブラシが歯肉に当たりにくくなります。
子どもたちの歯を虫歯から守る仕上げみがきは、子育ての大切な一部分です。周囲の大人がアシストして、お子さまの歯をしっかり守ってあげましょう。
●年齢に適した歯みがき方法
子どもは生後7ヵ月くらいの頃に前歯が生え始め、身体の成長に合わせて顎の骨や歯も発育が進んでいきます。お口の中の様子も変わりますから、その時々の成長にあった歯みがき方法が必要になります。
毎日の歯みがき習慣化に向けて、無理強いをせず、スキンシップのつもりで慣れていくことから始めましょう。
| 乳児期 | 赤ちゃんの舌に白っぽいカスが時々たまります。 水やぬるま湯で濡らした布を使い、拭き取ってあげましょう。 |
|---|---|
| 生後7~8カ月の時期 | 生後7~8カ月位になると、赤ちゃんに前歯が生えてきます。これまでと同じく、歯の汚れは布やガーゼで拭き取ってください。 |
| 生後1年を過ぎたら | この時期くらいから歯ブラシを使いましょう。 大人がみがきながら、お口の中に歯ブラシを入れるのに慣れさせます。 |
| 3歳を過ぎたら | この頃からお子さま自身で歯みがきをするようにしましょう。 もちろん、その後はお母さまが仕上げみがきをして、みがき残しがないかよくチェックします。 |
| 5歳を過ぎたら | 5歳位になったら、毎食後(朝・昼・晩)「1日3回みがき」をさせましょう。お母さまは、仕上げみがきを続けます。 |
| 6歳臼歯が生える頃 | 6歳位になると、一番最初の永久歯である六歳臼歯が生えてきます。この六歳臼歯は、食べカスがたまりやすく特に虫歯になりやすいと言われています。仕上げみがきの後に特に気をつけてチェックしましょう。 |
●歯みがきで大切なこと
歯みがきで大切なのは歯みがきの回数そのものではなく、お口の中に残った食べカスを落とすこと、細菌の塊であるプラーク(歯垢)を落とし、虫歯の原因を作らないことです。
一日に何回歯を磨いても、歯を「磨いている」だけでは虫歯は防げません。しっかり歯が「磨けている」ことで初めて歯みがきの効果が得られるのです。
この意識を持って、正しい歯みがきの仕方を身に着け、小さいうちから「食べたら磨く」「寝る前には磨く」という習慣を守って、お口のケアをしていきましょう。
特に眠っている間は、唾液の分泌量が減ることで虫歯菌が活発になり、みがき残しが虫歯につながりやすくなります。7歳くらいまでのお子さまには、周囲の大人が寝る前にしっかりと仕上げみがきをしてあげましょう。
当院では、お子さまがいつまでも健康な歯でいられるよう、お子さまとお母さまをトータルにサポートする、予防歯科を中心とした歯科治療を行っています。
子どもの歯並びやかみ合わせは、乳歯から永久歯に生え変わる過程で整います。乳歯は永久歯の生える足がかりをつくる大切な役割を担っています。そのため、乳歯が虫歯だらけだと将来的な歯並びやかみ合わせに悪影響を及ぼしかねません。
将来、大人になったときのためにも、子どものうちから虫歯になりやすい乳歯をきちんと管理し、守っていくことが大切です。
お子さまの成長を見守りながら、美しい歯並びやかみ合わせを育てていきましょう!
以下に、当院でおこなっている小児歯科の内容をご紹介します。

歯みがきの効果は正しく磨けて初めて発揮されます。
1人で歯みがきが出来るお子さまには、それまでの歯みがきの改善点を見つけ出し、より効果的な磨き方を指導するとともに、歯みがきの大切さをわかりやすく説明します。
また、仕上げみがきをする保護者の方には、仕上げみがきの指導もおこなっています。
合わない歯ブラシはみがき残しをつくる原因になりますから、自分に合った歯ブラシを見つけることも大切です。歯ブラシ選びにお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

フッ素には歯のエナメル質を丈夫にして歯を強くする効果があり、歯科では虫歯の予防処置に用いられています。
当院では、一般に売られていない高濃度(9000~9500ppm)の歯科医院専用フッ素を歯に塗布し、虫歯になりにくい強い歯質作りを促します。
1回のフッ素塗布だけでは高い効果は期待できないため、定期健診の際にフッ素塗布をおこないます。
また、フッ素には歯の再生(再石灰化)を促す作用と抗菌作用があります。ごく初期の虫歯ならフッ素塗布と食事指導・ブラッシング指導などを定期的に行うことで自然に治ることもあります。
フッ素は、私たちが毎日食べている海産物や農作物・お茶などにも微量に含まれていている、体に必要な栄養素の一つです。過剰摂取しない限りは安心ですので、用法を守ってご家庭でのフッ素洗口などをしていただくことは、安全で手軽な虫歯予防策と言えるでしょう。
歯の表面のエナメル質を酸に溶けにくい性質にします。
歯の表面は唾液に含まれるカルシウムやリンが再付着(再石灰化)することで、日々再生しています。フッ素はこの働きを助ける性質を持っています。
フッ素は虫歯の原因菌の働きを低下させます。細菌の働きが弱まると、酸の放出が減少し、歯も溶けにくくなります。
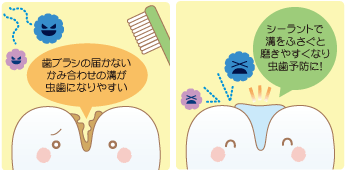
虫歯になりやすい奥歯のかみ合わせ面の溝を、食べカスが溜まらないようレジン(プラスチック)で埋めてしまう予防方法をシーラントと呼びます。これによって奥歯のかみ合わせに歯垢がたまりにくくなり、歯を削る事なく予防効果を得られます。特に虫歯になりやすい第一大臼歯(六歳臼歯)などによく使われます。
もちろん、シーラントをすれば歯みがきをしなくて良いということではありません。シーラントで覆われていない部分や、他の歯は引き続きケアが必要となります。知らず知らずのうちにシーラントが欠け、逆にそこに食べかすや虫歯菌がたまってしまうという事もありますので、定期検診をしっかりとおこないましょう。

サホライドはフッ化ジアンミン銀が主成分の薬剤で、殺菌作用と虫歯抑制作用を持っています。薬に含まれている銀の殺菌効果によって虫歯の進行を止めることができますが、その副作用として虫歯の部分が黒くなります。(健康な歯は変色しません)
乳幼児など、まだ歯を削る治療が難しい小さなお子さまで、乳歯の軽い虫歯の場合や、乳歯の生え変わり時期の場合に、虫歯の進行を遅らせるためにサホライドを歯面に塗ることがあります。
サホライドは、あくまで虫歯の進行止め(抑制)であって、虫歯を治癒したり、予防する方法ではありません。いわゆる対症療法であるため、処置後も周囲の歯を含めた定期検診が必要になります。
虫歯が治るわけではありませんので、虫歯にならない・虫歯を進行させない努力が何よりも大切です。
●子どもの定期健診
幼児から小学校高学年まで成長するにつれ、お子さまのお口の環境は「歯の生え変わり」「顎の成長」などのさまざまな変化を迎えます。健やかなお口のまま、将来の美しい歯並び・かみ合わせを目指すには、子どものうちの虫歯予防に加えて、定期的な歯並びやかみ合わせの診査が必要になってきます。また、初期の虫歯は自覚症状に乏しく、その中でも乳歯の虫歯は進行が速いのに対して痛みが出にくいと言われ、気が付いたときには深く進行してしまっていることがあります。虫歯を早期発見・早期治療し、更なる悪化を防ぐためにも、検診で定期的に口腔内の状況を把握し、年齢に合わせた予防法を受けていくことが大切です。
当院ではお子さまの成長に合わせて検診プログラムを設け、その時のお口の環境にもっとも有効な予防歯科治療の提供に努めています。
私達と一緒に、お子さまの将来を守って行きましょう!
大人ですら歯科治療の痛みにためらうことがあります。小さな子どもたちにとっては、尚更のことでしょう。当院では、痛みの少ない歯科治療を目指し、子どもたちの負担を少しでも軽減するため、さまざまなご用意をしています。
●麻酔注射の前に表面麻酔
 針による注入ではなく、歯肉に直接塗布することで効果を発揮する麻酔です。
針による注入ではなく、歯肉に直接塗布することで効果を発揮する麻酔です。
歯科治療において、唯一避けられない痛みが麻酔注射の針を刺す時だと言えるでしょう。
当院では麻酔注射の前に、注射針を刺す場所へキシロカインを塗布する予備麻酔をおこないます。
●体温に近い温度の麻酔液
 当院では、体温と同等に温めた麻酔液を使用しています。
当院では、体温と同等に温めた麻酔液を使用しています。
麻酔注射の痛みは、体温と麻酔液の温度との差とも関係しています。温めた麻酔液を使用することで、より注射時の痛みを緩和させることができます。
●電動麻酔注射器
 麻酔注射の痛みは、溶液を注入するスピードや圧力に大きく左右されるといわれています。当院では、コンピューター制御により痛みの少ない理想的なスピードで麻酔液を注入してくれる電動麻酔注射器を導入しています。
麻酔注射の痛みは、溶液を注入するスピードや圧力に大きく左右されるといわれています。当院では、コンピューター制御により痛みの少ない理想的なスピードで麻酔液を注入してくれる電動麻酔注射器を導入しています。
表面麻酔と併用することで、麻酔注射時の痛みを大幅に軽減してくれます。
●「思いやり」の治療
これがもっとも大切なことだと言えるでしょう。
精神的な苦痛は肉体的なものへとつながりやすく、お子さまの場合はそれがより顕著です。
当院では、できるだけ削らない治療、刺激の少ない治療を選択し、お子さまに合わせて治療のストレスを極力感じさせないよう心がけています。

生まれた時、赤ちゃんのお口の中には虫歯の原因菌は存在しません。
成長する過程のなかで、ご家族、お母さまのお口から、唾液を通した感染によって赤ちゃんのお口の中に虫歯菌が現れるようになるのです。
感染の原因となるのは、キスや口移しでの食事、同じ食器で食べさせることなど。ですが、だからといって、お子さまとの大切なスキンシップを止める必要はありません。
お母さまやご家族のお口のケアさえしっかりとできていれば、何の問題もないことなのです。
●お母さまの口腔ケアを
母子感染を防ぐには、一番赤ちゃんと多く接するであろうお母さまの口腔ケアを徹底し、お母さまのもつ虫歯菌を減らすことが先決です。妊娠中の歯周病の影響を考えると、お母さまには出産前からの口腔管理が望ましいですが、出産後は赤ちゃんが1歳半~2歳半くらいの頃が一番感染の危険性が高いと言われ、特に気をつけなければならない時期となります。
もちろん、お母さまだけではなく、赤ちゃんと触れ合う他のご家族も同様に口腔管理をしていくことが望ましいでしょう。
●口移しをしない、食器を共有しない
虫歯菌は唾液から感染するため、食べ物の口移しや噛んで柔らかくして与える行為は避けましょう。
同じスプーンや箸など、大人が使用したもので食べさせないようにしましょう。